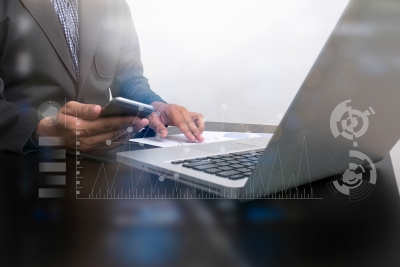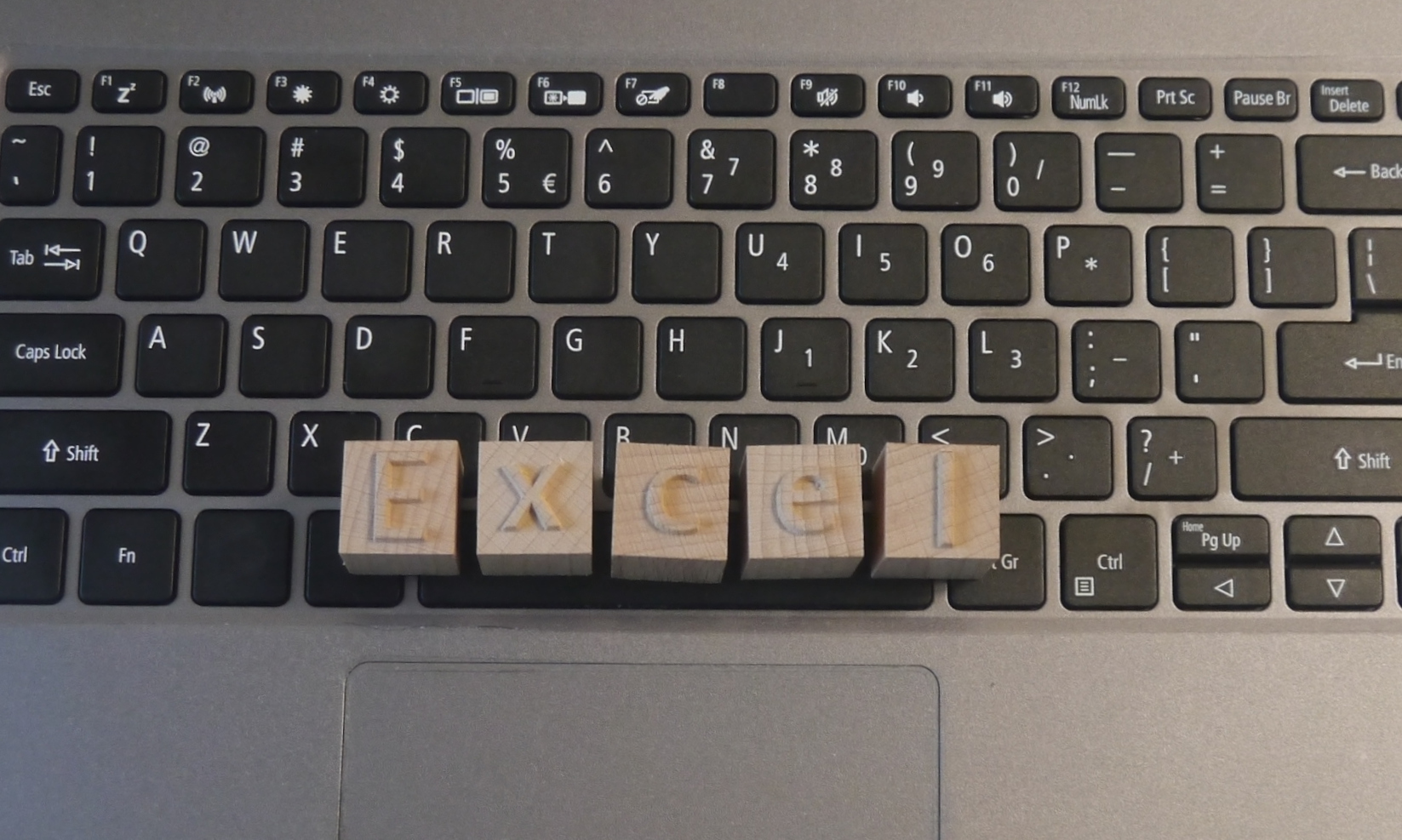足るを知る循環経済へ
column
2025年07月09日
水谷IT支援事務所代表 水谷哲也
昨今、大量生産、大量廃棄の経済活動が行き詰まりをみせています。そこで登場しているのが循環経済という言葉。循環経済を支えるためにデジタルでトレーサビリティを行う仕組みなどが拡がっていきます。
循環経済(サーキュラーエコノミー)へ
備蓄米放出でようやく米の値段も落ち着きはじめました。令和の米騒動と大騒ぎになりましたが、一方では年間約62万トンのお米が廃棄されています。国民1人あたりで換算すると毎日おにぎり1個を捨てています。お米だけでなく食品全体でみるとロスは年間約472万トンになります。考えてみれば宴会の食べ残し、賞味期限切れに気づかず冷蔵庫にほったらかしにしている食材など思いあたる点はいろいろあります。これ以外にもコンビニやスーパーでの弁当廃棄、規格外で売れない野菜などさまざまな食品ロスが発生しています。
我々の生活は大量生産、大量廃棄の経済活動に支えられてきましたが、経済が再現なく拡大することはなく限界がきています。持続可能な形で資源を利用する循環経済へ移行していかなければなりません。開催中の大阪万博では会場内にマイボトル洗浄機と給水スポットが設置され、自宅からポットの持参をすすめゴミをへらしています。
静脈産業という言葉もあります。製造業など製品を生み出す動脈産業に対して廃棄物を回収し再生や処分を行う静脈産業があります。心臓から体に送り出す動脈と心臓へ戻す静脈のように双方のバランスが必要です。今までは動脈重視でしたが食品ロスや廃棄物の回収ができないなど様々な問題が発生したことで静脈に注目が集まっています。
デジタルでトレーサビリティを行う
EUではデジタル製品パスポート(Digital Product Passport)という仕組みがすすんでいます。製品ライフサイクルのあらゆる段階で製品に関する情報を記録します。誰がどこで、どうやって作ったか、運送や廃棄も含めてデジタル保存することで企業や消費者はいつでもアクセスできます。トレーサビリティを行うことで循環経済を構築しやすくなります。
衣料品最大手であるザラ(ZARA)は世界で販売するすべての商品にICタグを縫い付けて販売をはじめます。小売店がつけるのではなく製造段階でメーカーがつけます。ICタグには原材料や製造場所などの情報が入ります。流通の各段階でICタグに追記し、最終的に修理が必要になった時や廃棄する場合、素材のリサイクルがしやすくなります。衣料品は特に廃棄が多く、日本国内では6割の衣料品が再利用されずに廃棄されています。
またリマニという動きがあります。リマニとは使用済みの製品から部品を回収し再び新品同様の製品として販売するリマニュファクチャリングの略で製品の長寿命化となり、究極のエコになります。
修理できる権利
近年、製品の修理はメーカーに頼まないとダメという慣行があり、これに対して自分で修理または修理業者に依頼する権利を認める動きが世界中に広がっています。これも製品の長寿命化につながりします。ただし需要を奪われる部品メーカーは大変です。そこでデジタル製品パスポートのように追跡できる仕組みを作り、部品が使われごとに部品メーカーに使用料を支払う仕組みを構築することが検討されています。
日本には老子の教えに由来する「足るを知る」という言葉があります。これから「使い捨て」でない「足るを知る」経済が必要になります。経済を委縮させずに環境を守ることがミソで、デジタルを使った仕組みづくりがすすんでいきます。
- 掲載しているブランド名やロゴは各社が所有する商標または登録商標です。
- この情報の著作権は、執筆者にあります。
- この情報の全部又は一部の引用・転載・転送はご遠慮ください。
関連コラム
ITコラムICタグの価格が1枚1円に