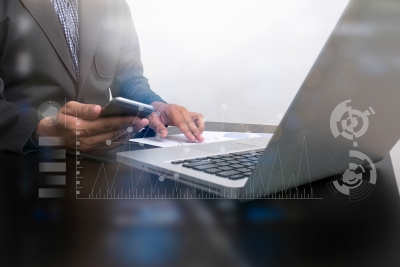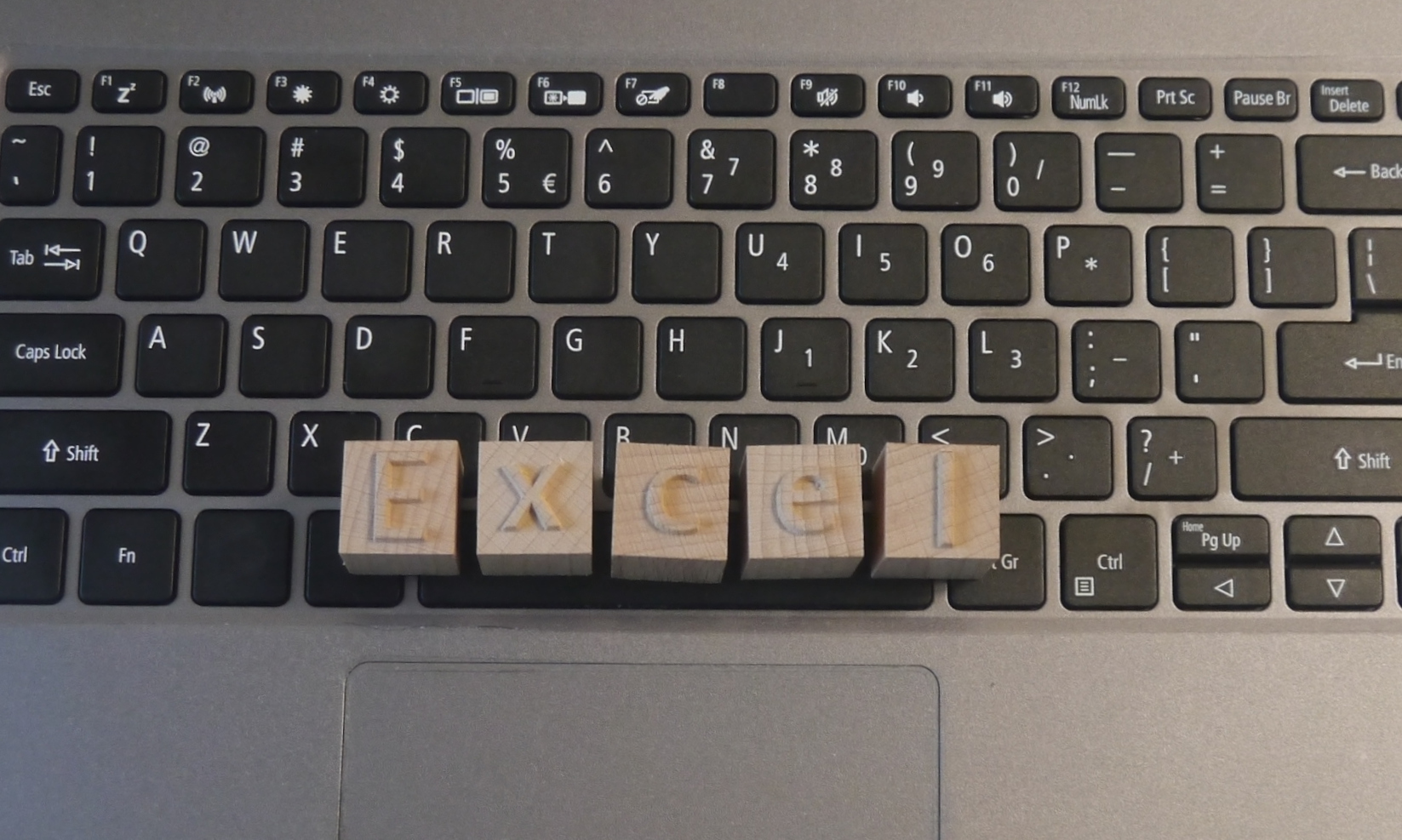100ドルパソコンで教育を
column
2025年03月12日
水谷IT支援事務所代表 水谷哲也
2007年にスマートフォンが誕生、2018年にPayPay決済がはじまり、またたく間にスマホを使ったビジネスやキャッシュレス決済が当たり前になりました。社会の変化が激しく、複雑で予測困難な時代になっています。これからは受け身ではなく、社会の変化を前向きに受け止め、豊かな人生を切り拓いていかなければなりません。そのためには教育が重要です。学校では一人一人が主体的・対話的に深く学べるように環境整備が行われています。
共通テストに情報1が登場
大学入学共通テストの問題が新聞に掲載され、字が小さいなと思いながら見ると今回、初めて情報1の問題が掲載されていました。2022年度以降に入学した高校生は新しい学習指導要領に沿って情報1を学習しています。共通テストで出題されたのは簡単なアルゴリズムの問題などですが、デジタル署名やIPアドレスといった自分が高校生の頃には聞いたことがない言葉が出ています。情報1は必修科目ですので、これで情報リテラシーは確実にあがりそうです。4年後には新入社員から「そんなパソコンの使い方をしているんですか?」と言われる時代が到来しそうです。
情報1を学習するためには環境整備が必要です。文部科学省は2019年にGIGAスクール構想を提唱し、全国の小中学校生に1人1台のパソコンと、高速大容量の通信ネットワークを整備しました。コロナ禍では登校できなくなったこともあり前倒しで実施されましたが、整備されたパソコンを使う学校と使わない学校での格差が指摘されており新しい課題になっています。
100ドルパソコンプロジェクト
日本では環境整備が進んでいますが発展途上国などでは、まだまだです。すべての子供たち一人一人にパソコンを提供しようと始まったのが100ドルパソコンプロジェクトです。マサチューセッツ工科大学(MIT)メディアラボの創設者であるニコラス・ネグロポンテが2005年に立ち上げました。
そして開発されたのが「OLPC XO」です。OLPC(One Laptop per Child)とはプロジェクトの名前で「子供一人に一つのノートパソコン」という意味です。ハードディスクの代わりにフラッシュメモリを使い、プログラミング、文書作成、イラストや作曲までもが可能なタイプの学習ソフトウェア「Sugar」が搭載されています。オープンソースとして提供されており利用や拡張が自由にできています。
発展途上国にはライフラインが整っていない国も多いため電力が不足しているような環境でもパソコンが使えるように省電力になっています。子供たちが屋外で使っても視認性が高いようになっていて、バックライトをオフにしてモノクロ表示できます。
一番の特徴は自分で修理できることです。壊れないパソコンを作ることは無理です。そこで子どもが自分で修理できるようにデザインされており、余分なネジをラップトップの中に入れています。
価格は100ドルを目指しましたが、なかなかうまくいきませんでした。現場の教師への研修の必要性は分かっても、お金がない非営利プロジェクトで行うのは無理でした。いろいろと批判もありましたが、ウルグアイの子供たちに60万台を提供するなど、世界中で約5,000万人に提供されました。先進国のユーザが2台のパソコン料金を支払い、1台は開発途上国の子供に送る運動などが行われましたがリーマンショックで頓挫します。
ラズパイで100ドルパソコンが実現
2012年、教育目的で開発されたのがシングルボードコンピュータ「ラズベリーパイ」です。ラズパイと省略して呼ばれています。LEDやセンサーなどの電子部品を取り付けられることからIoTで注目されました。ただリナックスベースのOSでマウス、キーボードやモニターはついていませんから、子供が使いこなすにはハードルが高いです。ラズパイは8000円~15000円ほどで売られており100ドルパソコンが実現できています。
- 掲載しているブランド名やロゴは各社が所有する商標または登録商標です。
- この情報の著作権は、執筆者にあります。
- この情報の全部又は一部の引用・転載・転送はご遠慮ください。
関連コラム
ITコラムプログラミング・ネイティブ世代が社会へ