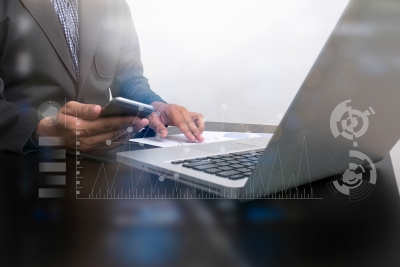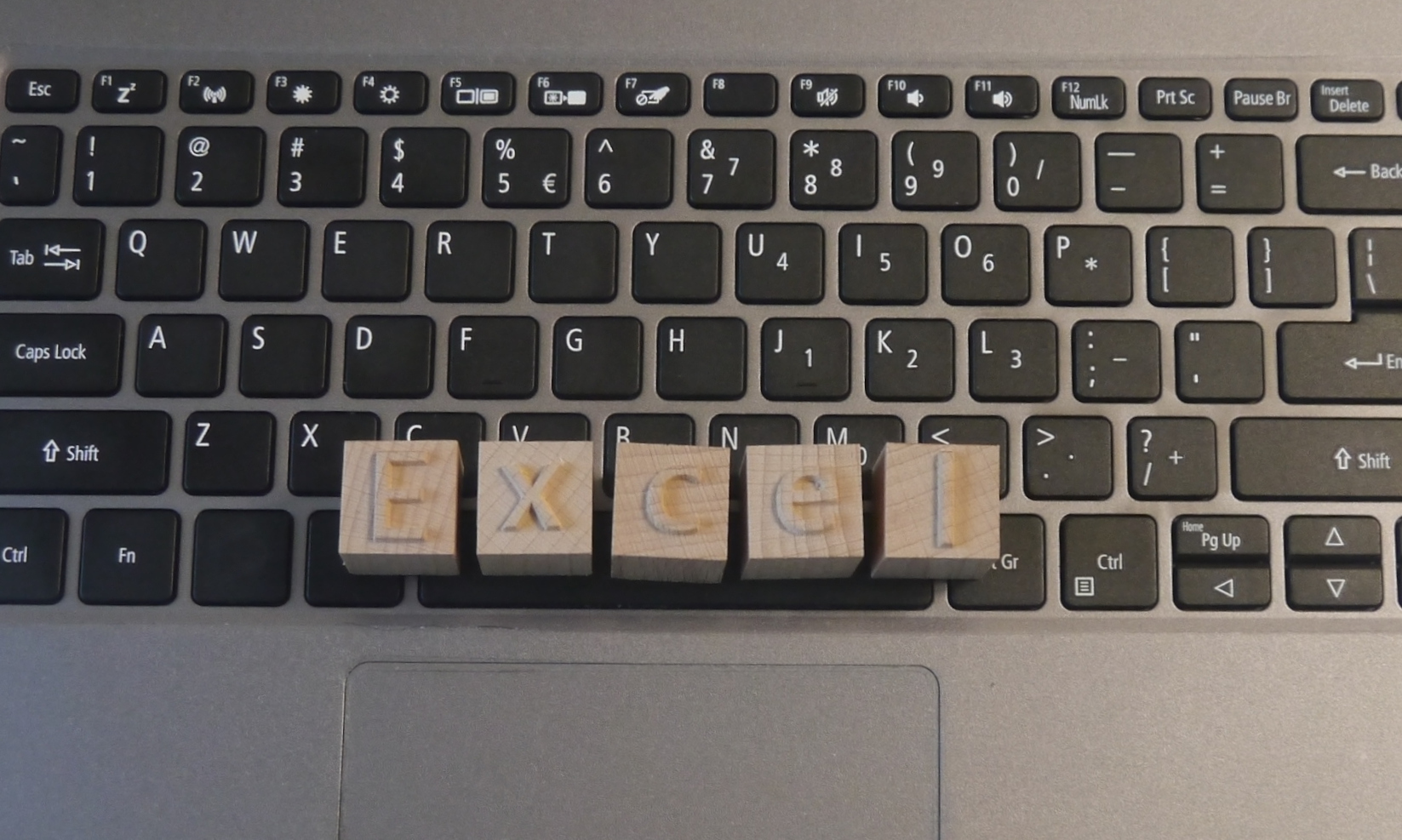紙の手形が2027年3月になくなります
column
2025年05月14日
水谷IT支援事務所代表 水谷哲也
手形は建設業や製造業など高額な取引や長期的な取引を行う企業でよく使われています。いよいよ紙の手形が2027年3月末に廃止され、「でんさい」(電子記録債権)に置き換わります。
手形は千年前から使われていた
江戸時代、旅で多額の現金を持ち歩くのは物騒でした。そこで両替商に現金を預け、手形を発行してもらいます。旅の途中、宿場などで指定された両替商や問屋に手形を提示すると、お金を受け取ることができました。
昔、証文に「必ず払うから」と手に墨をつけて手形を押したので"手形"と言うようになりました。手形は平安時代には登場していたので、少なくとも千年以上にわたり使われてきた伝統ある仕組みです。古代からずっと紙で運用されてきましたが2027年3月末に全廃されます。
でんさい(電子記録債権)がスタート
根拠となる電子記録債権法がスタートしたのは2008年12月です。2022年11月に全国にあった手形交換所(銀行の行員が手形を持ち寄って交換する場所)が全て廃止されました。各銀行では手形帳購入代金を2倍以上に値上げし、企業に紙の手形をやめるよう促しています。またメガバンクの多くは2026年9月末以降、紙の手形を取りやめるとアナウンスしています。
今後は手形の振出人など様々な情報をコンピューターで管理しなければなりません。それが「でんさい(電子記録債権)」です。紙の債権から電子債権に変わりますが不渡りのルールなどは今まで通りです。
振出期間は最長60日以内
手形にもう一つ大きな変更点があります。いつ換金できるかを決めた振出期間がありますが、現在は60日以内になっています。60日を超える振出期間の手形を振り出すと下請法違反になります。「でんさい」でも支払期日を振出日から60日以内に設定する必要があります。
「でんさい」を使うメリット
紙の手形では、紛失、盗難や火事の心配もあり、耐火金庫などに保管しなければなりません。遠方の企業と取引する場合は手形を郵送しなければならず、紙の手形を扱うにはコストも手間もかかります。「でんさい」に切り替えることでこれらの問題は解消できますが、他にもメリットがあります。
- 印紙税が不要
- 取り立てしなくてもすむ
- 1円単位で分割できる
- ストレスが減る
印紙税とは、契約書や領収書などの文書を作った時、契約金額によって課税される税金ですが、紙の契約だけにかかり、オンラインでの契約には課税されない不思議な税金です。「でんさい」に置き換えることで印紙税はゼロ円になります。
紙の手形を受け取ると、経理担当者は支払日がいつになるか期日管理しなければなりません。「でんさい」は、支払期日前にメールで知らせてくれます。また、銀行に出向いて取り立て依頼をしなくても、支払期日になると自動的に口座に振り込まれます。
100万円の紙の手形を受け取り、支払などで今すぐ50万円が必要なら手形を銀行に持ち込むことで、手数料はかかりますが現金化できます。手形割引という仕組みで、100万円すべてが現金化されます。「でんさい」は分割可能で100万円の「でんさい」があれば50万円を現金化し、残りは「でんさい」のままにしておけます。
経理担当者は銀行へ行く必要がなくなり、テレワークでも利用可能です。コロナ禍では手形処理のために会社へ出社せざるを得ませんでしたが、「でんさい」なら自宅でも可能です。また、記録内容はメールで通知されるため、確認や管理も容易です。期日管理でミスしないようにというプレッシャーから解放されます。
五十日(ごとび)という商習慣があります。五や十がつく日を決済日にしている企業が多く、営業が取引先に集金に行くことで道が混雑することをいいますが、営業は集金しながら取引先の状況をチェックしています。従業員との会話で会社に対する愚痴が多くなっていないか。事務所や倉庫がきちんと整理整頓されているか。在庫が急に増えたりしていないかなどです。今は振込が多く集金は減りましたが、定期的に取引先をまわり、経営がちゃんと回っているかどうかのチェックは「でんさい」であろうと必要です。
- 掲載しているブランド名やロゴは各社が所有する商標または登録商標です。
- この情報の著作権は、執筆者にあります。
- この情報の全部又は一部の引用・転載・転送はご遠慮ください。