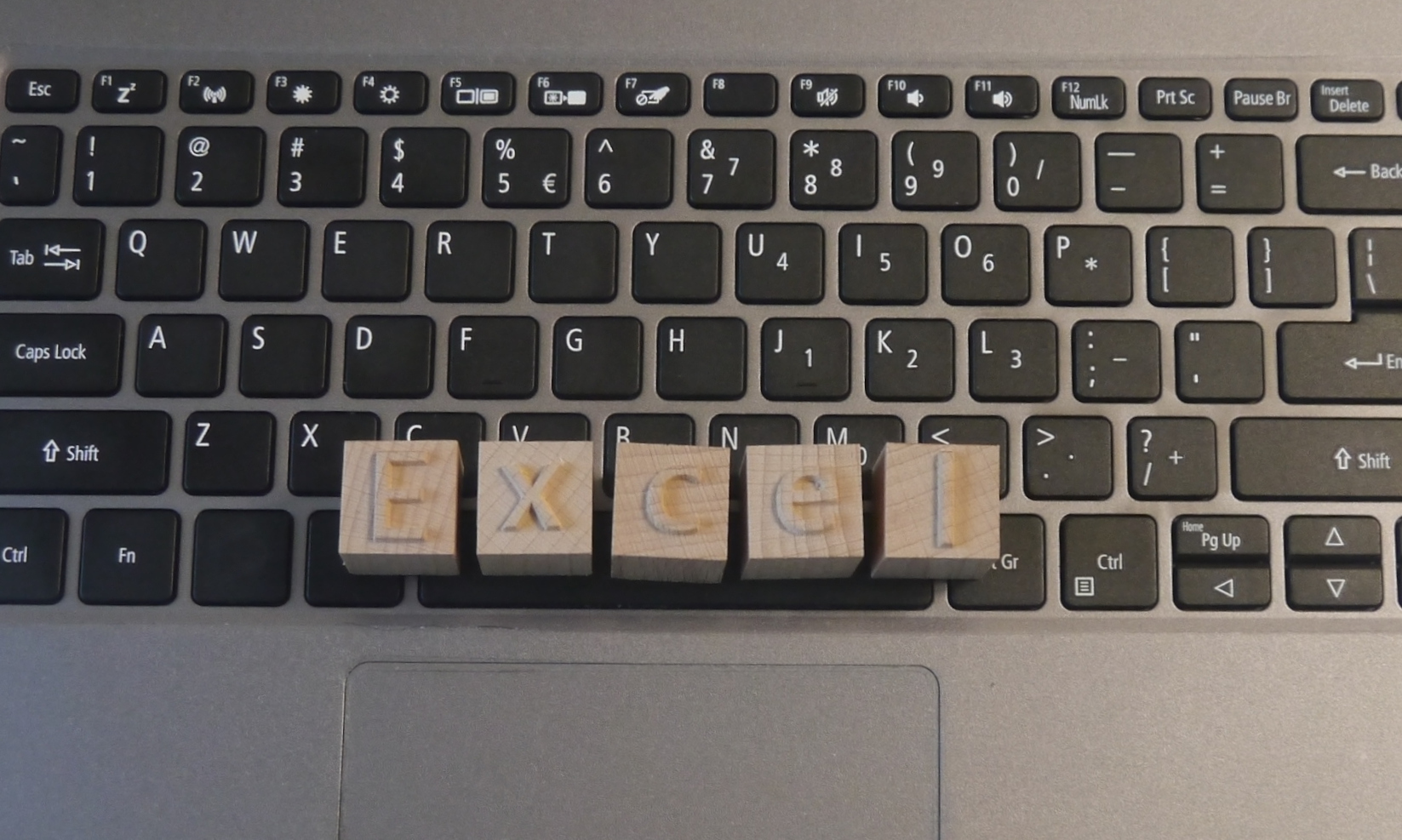被扶養者認定要件の変更について
column
2025年10月15日
社会保険労務士法人味園事務所 代表社員所長 味園 公一
令和7年10月1日より、社会保険(健康保険および厚生年金保険)制度における被扶養者の認定要件の一部が改正されました。特に、19歳以上23歳未満の家族(配偶者を除く)に関する収入要件が変更されることから、企業の社会保険実務においても一定の対応が求められる内容となっております。今回は、改正の背景や内容、注意点について紹介します。
改正の背景と制度趣旨
今回の改正は、令和7年度税制改正において創設された「特定親族特別控除」との整合性を図るために行われたものです。従来、所得税法上の扶養控除においては、19歳以上23歳未満の親族を「特定扶養親族」として、控除額を増額する制度が設けられていましたが、これに加えて、同年齢層のうち一定の所得水準にある親族を対象とする新たな控除制度が導入されました。
これに伴い、社会保険制度においても、同年齢層の家族に対する被扶養者認定要件の見直しが行われることとなりました。
改正内容の詳細
改正の対象となるのは、被保険者の家族のうち「年齢が19歳以上23歳未満の者(配偶者を除く)」です。これまで、被扶養者として認定されるためには、年間収入が「130万円未満」であることが要件とされていましたが、令和7年10月1日以降は「150万円未満」に緩和されました。なお、この「年間収入要件」以外の要件に変更はありません。
60歳以上または一定の障害を有する家族については、従来通り「180万円未満」が収入要件となっております。また、配偶者については今回の改正の対象外であり、引き続き「130万円未満」の収入要件が適用されます。
年齢判定の基準と注意点
年齢の判定は、所得税法に準じて、その年の12月31日時点の年齢により行われます。したがって、被扶養者の認定を受ける日現在の年齢ではなく、認定を受ける年の年末時点での年齢が基準となります。
例えば、令和10年10月に19歳の誕生日を迎える場合、その年の収入要件は「150万円未満」となりますが、令和14年中に23歳になると、同年の収入要件は「130万円未満」に戻ることになります。このように、年齢の変化に伴い収入要件が変動するため、対象者の誕生日や年齢の管理には十分な注意が必要です。なお、年齢は「誕生日の前日」において加算されますので、誕生日が1月1日である方は、12月31日に年齢が加算されることとなるため、特に注意が必要です。
なお、「学生であること」の要件は求められませんが、いわゆる「早生まれ」の対象者については、大学生であっても収入要件が130万円未満となる期間が長くなる傾向があり、誤認を防ぐための丁寧な説明が求められます。
収入の考え方と注意点
「収入」の範囲や考え方については、社会保険制度と所得税法上の違いがあるため、注意が必要です。
対象となる収入の範囲
社会保険制度においては、所得税法とは異なり、非課税とされる通勤手当や食事手当の他、失業等給付、傷病手当金や出産手当金等も収入として算定されます。したがって、同じ「収入」という表現であっても、制度ごとに含まれる範囲が異なるため、判定時には制度の違いを十分に理解したうえで対応する必要があります。
また、社会保険制度では「150万円未満」、所得税法では「150万円以下」といった微妙な表現の違いも存在するため、実務上の混同を避けるためにも、制度ごとの定義を明確に区別することが重要です。
年間収入の考え方
社会保険制度における年間収入とは、過去の実績ではなく「認定時点およびその後1年間の見込み収入額」を指します。給与収入の場合、130万円未満では月額108,334円未満が目安ですが、150万円未満では月額125,000円未満が目安となります。
このように、所得税法とは異なる収入の捉え方がされているため、認定時には見込み収入の根拠資料(給与明細、雇用契約書等)の提出が求められる場合があります。
おわりに
今回の改正は、令和7年10月1日以降に適用されています。令和7年10月1日以降の届出であっても、令和7年10月1日より前の期間について認定する場合、19歳以上23歳未満の被扶養者にかかる年間収入の要件は「130万円未満」で判定されます(令和7年9月1日の扶養追加手続きを遡って行う場合等)ので、注意が必要です。
その他、年収の壁支援強化パッケージの一つとして、繁忙期等の事情により収入が一時的に150万円を超える場合でも、勤務先の証明等により認定を継続できるケースがあるため、該当する従業員には個別の案内を行うことが望ましいでしょう。
- 掲載しているブランド名やロゴは各社が所有する商標または登録商標です。
- この情報の著作権は、執筆者にあります。
- この情報の全部又は一部の引用・転載・転送はご遠慮ください。
関連コラム
社労士コラム「年収の壁・支援強化パッケージ」について【前編】