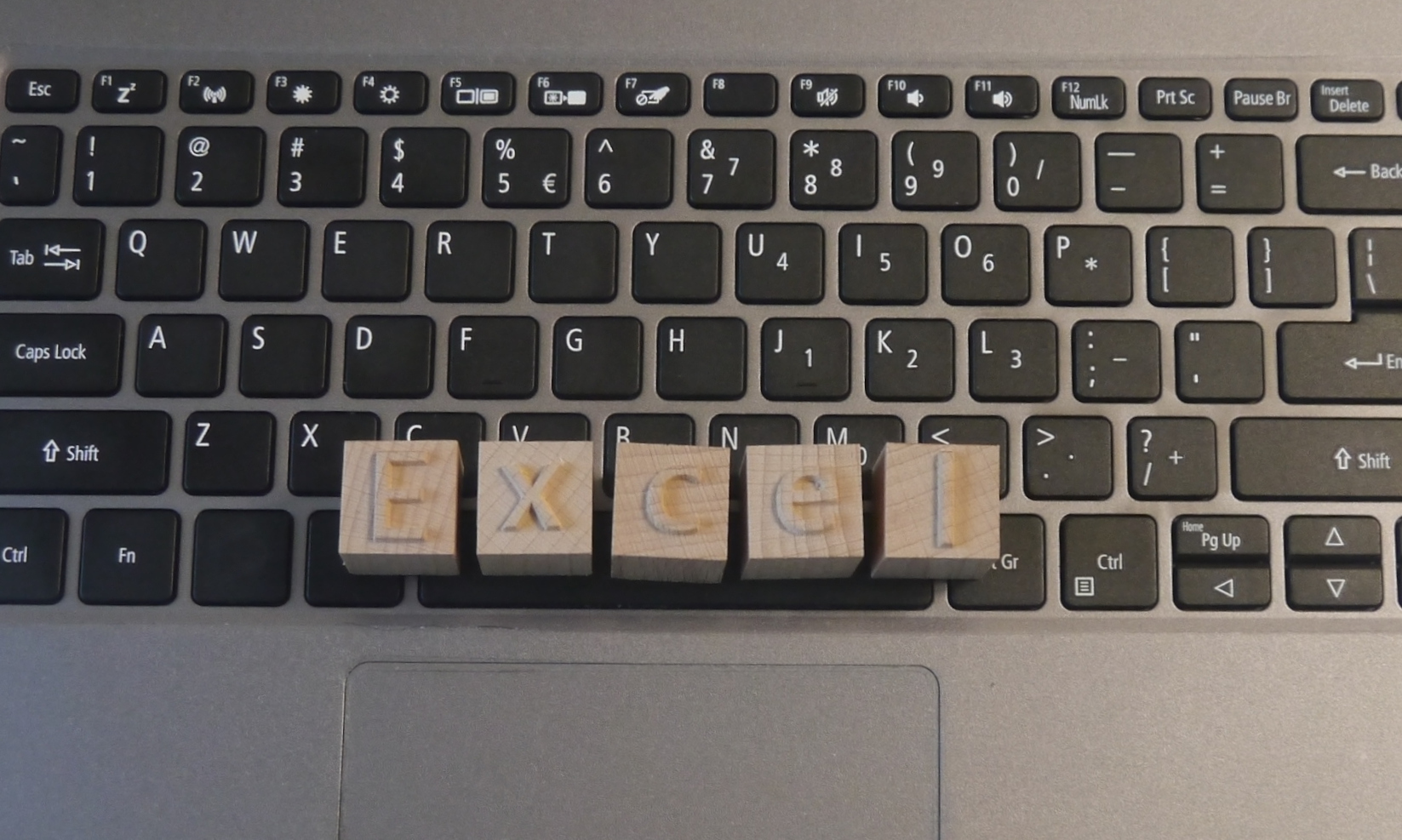同一労働同一賃金見直しへ
column
2025年03月19日
社会保険労務士法人味園事務所 代表社員所長 味園 公一
厚生労働省は2025年2月5日、労働政策審議会同一労働同一賃金部会を6年ぶりに開催し、2018年に成立した働き方改革関連法により施行された「同一労働同一賃金制度」の見直しに向けた議論を開始したとのことです。そこで今回はその議論の論点と、今後の対応について紹介します。
制度見直しについての背景と論点
同一労働同一賃金制度については、2018年の働き方改革関連法により、同一労働同一賃金に係る規定が2020年4月1日(パートタイム・有期雇用労働法の中小企業への適用は2021年4月1日)から施行されました。この働き方改革関連法には、法律の施行後5年を目途に検討・見直しをする旨が規定されています。今回、施行後5年の見直し規定を受けて、議論が開始されました。
待遇差の説明義務の強化
現在のパートタイム・有期雇用労働法及び労働者派遣法に基づく同一労働同一賃金制度では、「労働者が求めた場合にのみ」企業は待遇差の内容や理由を説明する義務があります。しかし、労働政策研究・研修機構による調査では、「待遇差の内容や理由の説明を企業に求めたことがある労働者」は8.0%で、そのうち説明を受けたのは5.4%でした。
説明を求めた労働者が少ない現状について、労働者委員からの「説明を受けなければ自身の待遇が不合理なものなのか知ることができず、是正を求めることもできない」との指摘を受け、「労働者の求めがあったとき」という要件の削除が議論されています。加えて、労働者へのさらなる制度周知が重要という議論もあります。
非正規労働者への支援強化
現在のパートタイム・有期雇用労働法及び労働者派遣法に基づく同一労働同一賃金制度では、正規雇用労働者と非正規雇用労働者の格差是正が目的ですが、それに伴い、企業のコスト負担が増加し、一部では非正規雇用労働者の雇い止めなどが懸念されているという状況があります。
そのため、企業が適切な待遇改善を行うための「ガイドラインの見直し」や、「正社員転換制度の促進」も論点となっています。
今後の対応
議論されている論点を整理し、今後制度が見直されることを見込んで、企業は以下の点を意識して対応を進めることが望ましいでしょう。
待遇差のチェックと見直し
まずは同一労働同一賃金に関するガイドラインを改めて確認します。そして、正規雇用労働者と非正規雇用労働者の賃金・手当・福利厚生等を比較し、不合理な差がないかガイドラインに沿って検討します。検討した結果、必要に応じて待遇の改善を実施しましょう。
説明義務への備え
「労働者からの求め」がなくても、待遇に関する情報を分かりやすく開示することが望ましいです。また、社内規定や契約書の内容を整理し、待遇差についての合理的な説明ができるよう準備しておきましょう。その他、新規採用時に労働条件提示とあわせて待遇に関する説明を丁寧・明確に行うことが重要であると考えます。
非正規雇用労働者のキャリアパスの整備
不本意に非正規雇用労働者となっている方も存在するため、「正社員転換制度」の導入や制度周知を検討しましょう。また、キャリアアップのための研修やスキルアップ支援を行うことも望ましいでしょう。その他、必要に応じて賃金制度や評価制度の見直しを行い、透明性のある昇給・昇格の基準や制度を構築することも検討します。
労働局と労働基準監督署の連携強化
補足としての紹介になりますが、2023年3月から労働局と労働基準監督署の連携が強化されており、2024年度地方労働行政運営方針においても、非正規雇用労働者の処遇を改善するため、同一労働同一賃金の遵守徹底に向けた取組みを引き続き強化していくとのことです。
具体的には、労働基準監督署が定期監督などで企業を訪問した際に、非正規雇用労働者の有無のほか、諸手当・賞与・基本給等の待遇差を確認し、その結果を踏まえて、労働局(雇用環境・均等部門)が報告徴収の対象企業を選定することで、是正指導の実効性を高めています。
おわりに
労働政策研究・研修機構による調査では、同一労働同一賃金に関して、非正規雇用労働者に対して待遇の新設・拡充を行った企業割合をみると、大企業では、慶弔休暇が50.7%、基本給44.6%、賞与37.6%で、中小企業では、基本給が57.0%、賞与41.1%、基本給の昇給の仕組み40.0%という回答割合とのことです。
ガイドラインに沿って、非正規雇用労働者を慶弔休暇の対象にすることや、非正規雇用労働者に対しても貢献度に応じて賞与を支給すること等、できるところから検討することが望ましいと考えます。
今後、労働基準監督署や労働局から、同一労働同一賃金規制の履行状況について確認を求められる可能性が高いことを踏まえ、不合理と判断される可能性のある待遇差を洗い出し、待遇を見直すといった対応が必要でしょう。
また、待遇差を設ける場合には、各待遇差につき合理的な説明ができるよう準備をしておきましょう。
- 掲載しているブランド名やロゴは各社が所有する商標または登録商標です。
- この情報の著作権は、執筆者にあります。
- この情報の全部又は一部の引用・転載・転送はご遠慮ください。
関連コラム
社労士コラム同一労働同一賃金に関する最高裁判決