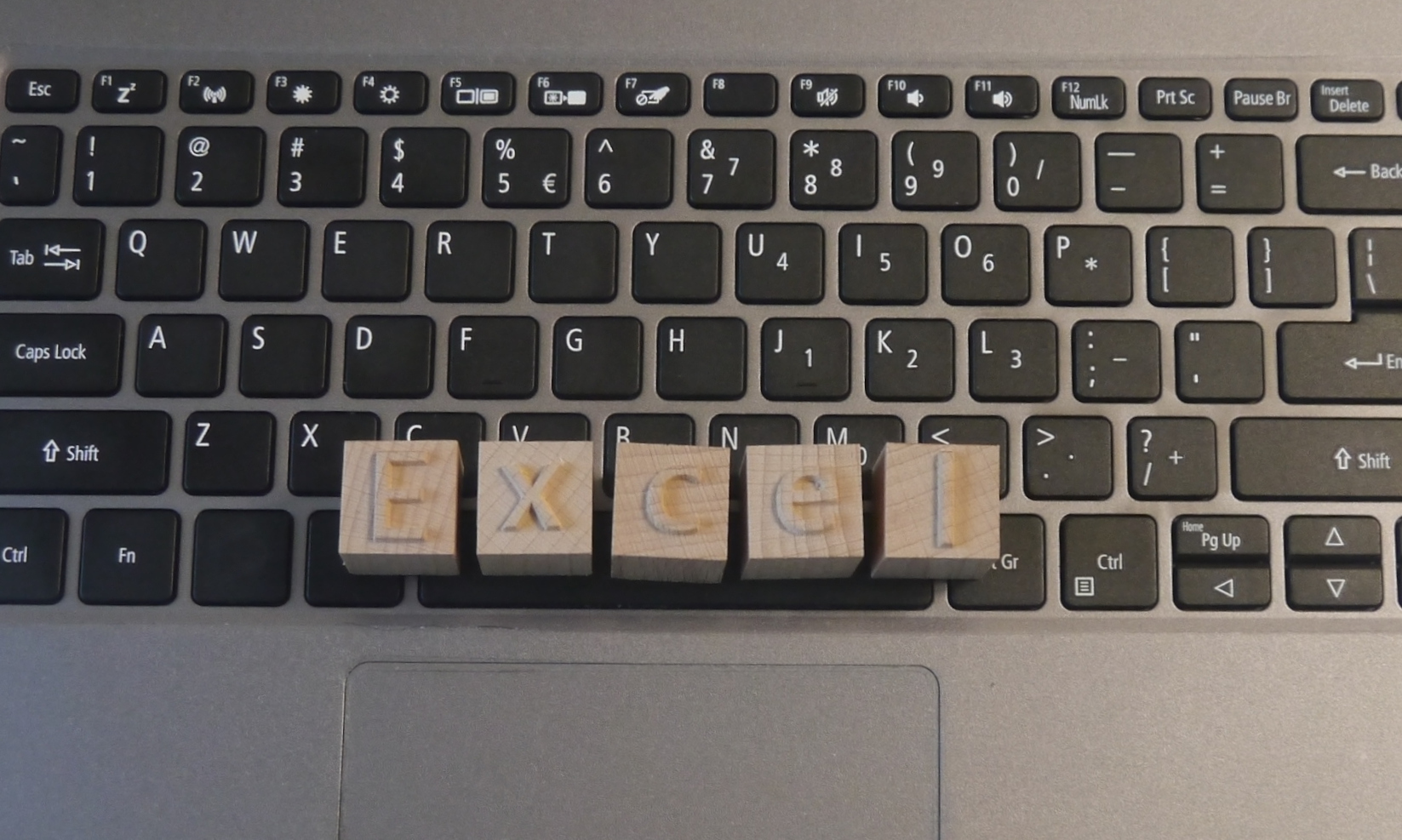雇用保険法の改正について
column
2025年04月16日
社会保険労務士法人味園事務所 代表社員所長 味園 公一
雇用保険法の改正により制度の変更や新たな給付が創設されることとなりましたので、今回は2025年4月1日の改正内容についてご紹介します。
制度見直しの背景
今回の改正は、多様な働き方を効果的に支える雇用のセーフティネットの構築、「人への投資」の強化等のため、教育訓練やリ・スキリング支援の充実を目的として、高年齢者の雇用確保措置の進展や労働人口の減少といった社会情勢の変化に応じて必要性が薄れた制度が廃止や縮小される一方で、拡充や創設される制度もあり、財源の再配分が行われています。
制度の変更点
従来の制度から変更となるのは、次の4点です。
- 高年齢雇用継続給付の給付率の引き下げ
- 就業促進手当の見直し
- 基本手当の給付制限期間の短縮
- 育児休業給付金の延長手続きの厳格化
変更内容の概要
- 高年齢雇用継続給付の給付率の引き下げ
- 就業促進手当の見直し
- 基本手当の給付制限期間の短縮
- 育児休業給付金の延長手続きの厳格化
賃金が60歳等到達時賃金から75%未満に低下した場合に、実際に支給された賃金額の最大15%が給付されていましたが、最大で10%に引き下げられることとなりました。
なお、高年齢継続給付については、段階的に縮小し、いずれ廃止となることが決まっております。
労働人口の減少により、以前に比べ政策的に再就職を促進する必要性が薄れたことから、就業促進手当のうち制度利用者が限定的となっている就業手当が廃止され、また、1年を超えて雇用が見込まれ、かつ、就業促進定着手当(6か月以上再就職先で勤務した場合に、基本手当の残日数の最大40%が支給されたもの)についても一律20%の給付に引き下げが行われることとなりました。
自己都合離職者に対しては、基本手当(いわゆる失業給付)の受給に当たっては、待機期間満了(受給資格確認日から7日間)の翌日から原則2か月の給付制限がありましたが、2025年4月1日以降の自己都合離職者については、給付制限が原則1か月に短縮されることとなりました。
また、自己都合の離職回数が5年以内に2回を超える場合は、原則1か月の給付制限に加え3か月の給付制限がかかりますが、離職期間中や離職前1年以内に自ら雇用の安定及び就職の促進に資する教育訓練を行った場合には、いずれの給付制限も解除されることとなりました。
育児休業給付金を延長することを目的として、あえて自宅や勤務先から遠い保育所等に申込みを行うといった事例があるとの問題提起が地方自治体から行われたことから、育児休業給付金の延長手続きの際、これまで添付していた「市区町村が発行する保育所等の利用ができない旨の通知(入所保留通知書等)」の他、「育児休業給付金支給対象期間延長事由認定申告書」と「市区町村に保育所等の利用申し込みを行ったときの申込書の写し」の計3点の提出が必要となりました。
書式や詳細な要件については厚生労働省のHPに掲載されておりますので、あわせてご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000160564_00040.html創設された制度
今回の改正により創設された制度は、次の2点です。
- 出生後休業支援給付金
- 育児時短就業給付金
創設された制度の概要
- 出生後休業支援給付金
- 育児時短就業給付金
共働きを推進するため、同一の子に対して子の出生から一定期間に両親とも14日以上の育児休業を取得等した場合に、(出生時)育児休業給付金とあわせて最大28日間出生後休業支援給付金が支給されます。
(出生時)育児休業給付金とあわせた給付率は休業開始時賃金日額の80%となり、社会保険料が免除されることや雇用保険からの給付が非課税であることから、給付額が給与額の手取相当となるよう創設された制度となります。
仕事と育児の両立支援を目的として、2歳未満の子を養育するために、育児休業給付金の支給対象となる育児休業から引き続いて育児時短就業する場合に、育児時短就業期間中に支給された賃金額の最大10%相当額が支給される制度となります。
上記の「出生後休業支援給付金」とあわせ詳細については、厚生労働省のHPに掲載されている「育児休業給付の内容と支給申請手続(令和7年1月1日改訂版)」に記載されていますので、こちらもご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001461102.pdfおわりに
今回の改正により育児関連の手当については、改正前に比べ添付書類や確認事項が、増加しております。対象となる見込みの方がいらっしゃる場合は、ご紹介した資料も活用しながら事前に準備を進められると良いでしょう。
- 掲載しているブランド名やロゴは各社が所有する商標または登録商標です。
- この情報の著作権は、執筆者にあります。
- この情報の全部又は一部の引用・転載・転送はご遠慮ください。
関連コラム
社労士コラム2025年の法改正情報